辞め官コンサル❹『自治体から見た“辞め官コンサルタント”』

「せっかく民間委託に踏み切ったのに、この提案書、行政臭プンプンじゃん❗️」
実はこれ、ある公共施設の運営事業者を選定した際に、私が提案書に対して抱いた感想です。
公務員でありながら、そんな不満って⋯⋯正直なところ、けっこうありました。そのたびに、「提案書の作成に官業出身者が関与したかも」と、行政臭さの原因を推測したものです。
今回は、“辞め官コンサルタント”の姿が提案書の向こうに透けて見える⋯そんなとき、自治体は『かつての同業者』をどう感じ、どう対峙してくるのか、私自身の経験をまじえて考察します。
辞め官コンサルの提案書関与は、自治体にとって、😇GOOD?or BAD?😈
◾️ 提案書に現れる“辞め官”の影
提案書の『行政臭さ』に関連して、具体例を二つ紹介しましょう。

《 その❶ 》公共施設の管理運営受託を望む企業が、提案書の中で施設の責任者に公務員OBを指名してくるケース。あるいは、現場で働いていた公務員をそのまま社員に採用して就労させるケース。
☝️自治体側が、雇用の継続を条件とするなど、現場職員の丸抱えを望む場合はOKです。ただし、自治体が民間ならではの柔軟なマネジメントを期待する場合、その提案は改革意欲や効率性の点で、どうにも物足りなく映るでしょう。
《 その❷ 》提案書の生命線とも言える企業としての「取り組み方針」や「業務への認識」に主張が感じられないケース。民間ならではの姿勢を前のめりに示すべきところ、自治体が既に策定している計画書や条例の該当部分をほぼコピペのように淡々と転記していました。
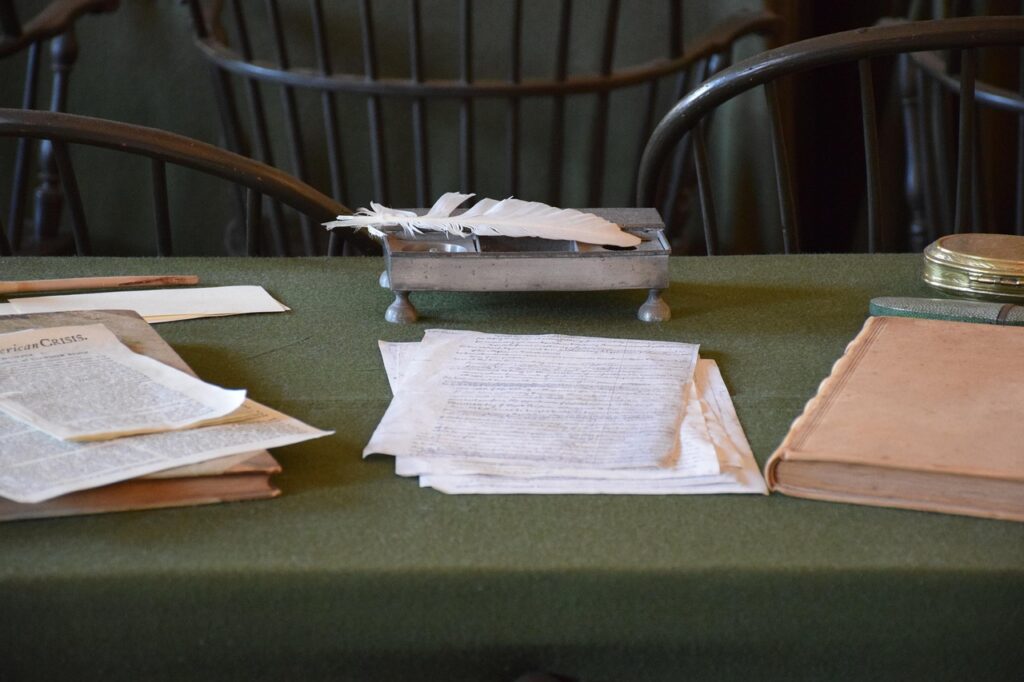
☝️確かに正確です。なにせ行政の計画書や公文書をコピペしてるのですから。しかし、受託企業としての積極的な姿勢や意欲、新しい発想などの力強さが提案書から失われる危険性があります。
❶❷いずれの場合も、自治体が「安全策に偏りすぎではないか」と、提案企業の姿勢に疑念を感じれば、『事業への意欲』『先進性や斬新さ』などは低い評価となるでしょう。その原因が、辞め官コンサルタントの指導や助言だったとすれば⋯⋯
ありがたいようで扱いづらいとも言える“辞め官”が関与したことによって、提案書の勢いや輝きが失われれば、それはメリットどころか逆効果ということになってしまいます。
◾️ 頼れる存在 煙たい存在

官業側から見る“辞め官コンサル”には、次のような二つの側面があります。
- 頼れる存在
辞め官は、様々な計画や条例規則などの行政関係知識を企業側に伝え、選考委員会の審査ポイントを理解して提案書を現実的に整えます。提出する側だけでなく、受け取る側の自治体にとっても、行政知識の深さと行政の経験値は評価に値する場合が多く、大きな安心感を与えます。
- 煙たい存在
一方で、行政寄りの知恵を吹き込むことで、企業の提案書から民間ならではの発想や柔軟さを後退させることがあります。結果として、これまでと変わらない安全で穏当な提案書にまとめられ、行政直営と大差のない印象を与えます五。y

多くの自治体では、「提案の中に官業の知見はあって欲しい。だからと言って提案全体が『官流』じゃ困る!」という二律背反の感情を持っています。
そんな中、“辞め官コンサルタント”が進むべき道は、ただ一つです。
企業の提案活動を支えて自治体の公募プロポーザルを勝ち獲ること。その結果、自治体の公共目的実現にも貢献すること。
そう、『一挙両得』に他なりません‼️
◾️ 公務の本質 と“異分子”の登場
ここで視点を変えます。官民論争に欠かすことのできない「どうして、こうも公務員は堅物ばかりなの?」「民間では、規則どおりはNG!」に関連して、公務の社会学的な考察を試みましょう。
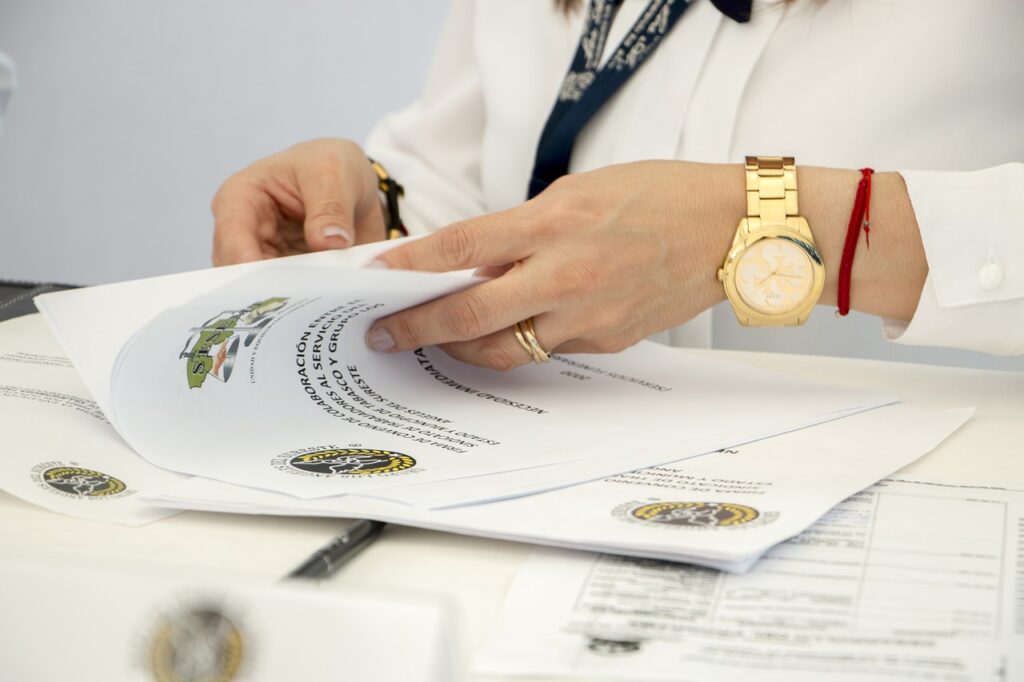
官業に身を置く大多数の公務員は、“ルールを守るプロフェッショナル”たる存在として働いています。もともと、公平性・正確性を重んじる公務員の姿勢は、社会の安定的な運営に欠かせないからです。
競争社会に生きる民業から見れば、それは『悪平等』に映るかもしれません。しかし、公務員が執拗にルールを遵守する姿勢を持たなければ、社会は『万人の万人に対する闘争(出典;トマス・ホッブス『市民論』)』の状態に陥るのです。
一方、時代の変化に応じて、あるいは変化を先取りして、創出や改革に踏み出そうとする“異分子のチャレンジャー”が公務員の中にも存在します。

長い行政経験を通じて、私は、そうした公務員の輩出を職場の内外で見てきました。いま私が協働しているスタッフは、まさにその「異分子」の精神を知る者たちです。
彼らは、官業の知見を積み重ねた公務のプロフェッショナルであると同時に、行政の中にあって、進歩と革新を好むキラリと光る存在でした。
競争の激しいコンサルタント業界を見渡しても、希少かつ貴重な存在と言えるでしょう。
◾️ 自治体からも頼られる“越境者”

「この提案書、どうせ辞め官が『計画書をコピペしておけば安全』とでも助言したんだろう」
自治体から、そんなマイナス評価を受けるのでは、辞め官コンサルタントを導入した意味がありません。
辞め官コンサルを「煙たい存在」ではなく、自治体にとっても「頼れる存在」として企業に根づかせること。これも、パートナーシップ・コンサルタンツ(PSC)の社会的使命と考えています。
求められているのは、官業の事情に精通した行政プロフェッショナルの知見を活かして企業を指導・誘導し、民間ならではの柔軟性や創造性、瞬発力をうまく公募提案書に着地させること。
その二つの手腕が発揮されるとき、辞め官コンサルタントは単なる“元公務員”ではなく、官と民の双方に信頼される“越境者”となって、企業の提案内容に輝きを与え、自治体をも側面から支える存在となります。
官民連携の担い手である自治体と企業にとって、辞め官コンサルタントこそ強力なパートナーと言えるでしょう。
PSCから皆さんへ

『パートナーシップ・コンサルタンツ(PSC)と共に歩む企業の提案書は、自治体にとっても最良の選択肢となる』
その確信を胸に、私たちは企業に伴走します。
PSCの辞め官コンサルタントは、官民が双方の力を融合させ、より良い公共サービスを生み出すために力を尽くすコラボレーター。官業スタイルに偏らず流されず、自治体の未来を見据え、民間の挑戦を支えつづけます。
官業を知るものだからこそ、民間にいても自治体の抱える課題にまっすぐ向かうことができる。私は、そんなPSCの役割を多くの企業、団体、個人の皆さんにお届けしたい。そう思っています。
追伸;官業に従事する皆さんへ
パートナーシップ・コンサルタンツ(PSC)が、クライアントの企業、団体、個人から求められているのは、ただ行政の制度や規則に詳しいことだけではありません。
官業経験があるからこそ見える課題を提示し、地に足のついた解決策へ導いてきた実績が、評価をいただいていると認識しています。また、官業側にいる皆さんが大切にしている『公共の利益』の精神を噛み砕いて、民業側にいる皆さんに理解していただくことで、新たな視点を得ることができると好評をいただいています。
─PSCと共に歩むことは、官と民の力を融合させ、より良い公共サービスを生み出すうえで最良の選択
私たちは、官民双方にそう感じていただけるよう、研鑽を重ねています。
次回(第5回)予告
次号ブログ『辞め官コンサル』の第5回は、シリーズを締めくくる最終回。官民連携が真に機能する社会をめざして、“辞め官コンサルタント”が今後果たすべき役割と意義などについて、未来志向で考察します。
ご期待ください!


